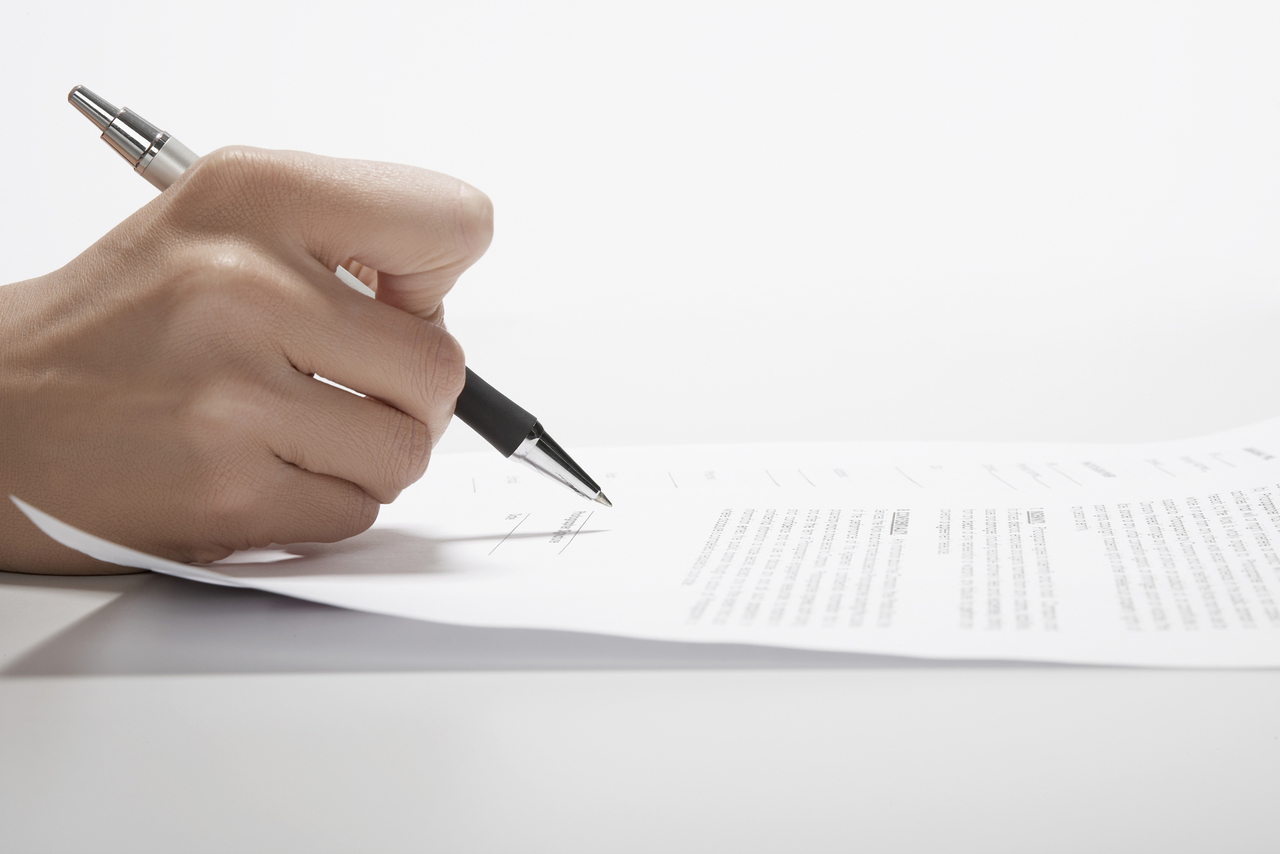愛知・名古屋周辺の相続・家族信託のご相談なら
名古屋相続・生前対策相談室
〒460-0008 名古屋市中区栄一丁目12番6号 秋月ハイツ3階
名古屋市営地下鉄 「伏見駅」徒歩5分
受付時間 | 9:00〜18:00 |
|---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|
任意後見制度とは
任意後見制度とは
任意後見制度とは、将来の判断能力の低下に備えて、後見の事務の内容と後見をする人を事前に決めておく制度のことをいいます。
本人が自ら選んだ後見人候補者に対して、精神上の障害により判断能力が不十分の常況になった場合に、生活、療養看護及び財産管理に関する代理権をあたえる委任契約を結びます。そして、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その効力が発生します。
任意後見契約は、任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が発生する旨の特約を付すること及び公証人に公正証書による契約書を作成したもらうことが必要です。
任意後見と法定後見の違い
任意後見と法定後見の違いは多くありますが、一番の違いは任意後見が「自らの意思表示」で後見人を選ぶのに対し、法定後見は自らの意思によらず後見人が選任されてしまうことです。
任意後見制度は、自分の死後の遺産の承継、管理などを定める遺言に似た制度で自分に何かあったときのための生前対策の一種といえます。
法定後見制度は、本人の財産に損害が及ぶことがないよう、本人の財産を守る制度です。選ばれた後見人は、財産をプラスにするというよりは、マイナスにならないよう保全するといった管理を行います。本人が判断能力が不十分になってしまっている以上、本人が願う管理方法となるとは限りません。
委任する事務の内容
任意後見契約において、委任をする事務は、本人の生活、療養看護又は財産の管理に関する事務となります。たとえば預貯金の管理、不動産の売買など財産管理に関することや施設入所契約、医療契約の締結など療養看護に関することなどが該当します。
委任する内容については、代理権付与の対象となる法律行為を明確に特定して記載することが必要です。
任意後見契約はどのようなことでも委任できるわけではありません。結婚、養子縁組など一身専属的な権利については、任意後見契約に盛り込むことはできません。
任意後見の流れ
任意後見制度を利用するには、公証役場で任意後見契約を締結する必要があります。具体的な流れは下記のとおりとなります。

支援する人を決めましょう。
任意後見の内容の決定
自分が判断能力が不十分になったときに、支援してくれる人(任意後見人)を決めます。自分の大切な財産を管理してもらうので、十分に信頼できる人を選ぶことが重要です。
また、任意後見は契約で定められたことを基に支援をします。できること、できないことを明確にする必要があります。

任意後見契約を公正証書で結びます。
任意後見契約の締結
任意後見契約は公証役場で公正証書よる契約を結ぶ必要があります。事前に公証人と契約内容について、打ち合わせをし、公証役場に出向いて契約を結びます。
任意後見契約を締結するとその内容は登記されます。
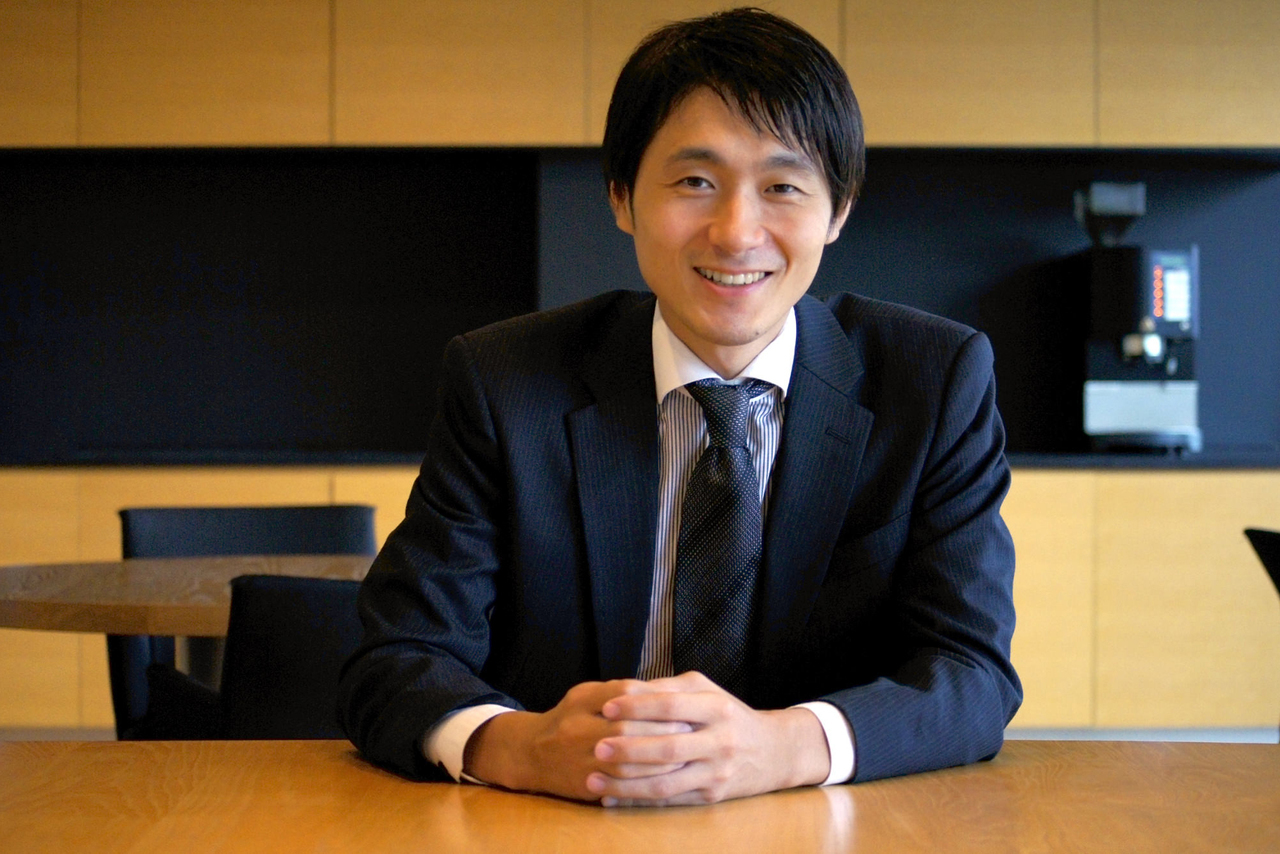
司法書士や弁護士などが選ばれることが多いです。
任意後見監督人の選任申立
本人の判断能力が低下してきたら、本人や任意後見受任者、4親等内の親族等が家庭裁判所に対して、任意後見監督人の選任の申立をします。
任意後見制度は、任意後見監督人が選任されることによって効力が生じます。

任意後見人としての支援が始まります。
任意後見事務の開始
任意後見監督人の選任の審判が関係者に審判がされ、異議申立がなければ任意後見契約の内容の支援が開始されます。
支援が開始されると、任意後見監督人は任意後見人を監督します。
任意後見制度に必要な費用
任意後見契約時に必要な費用
公証役場の手数料:1契約につき、1万1000円、それに証書の枚数により加算あり
印紙代:2,600円
登記嘱託料:1,400円
書留郵便料:540円
正本謄本の作成手数料:1枚250円×枚数
任意後見監督人選任申立時に必要な費用
申立費用:収入印紙 800円
収入印紙 1,400円(登記嘱託費用)
郵便切手 約4,000円
鑑定費用:5万円(必要がある場合)
その他戸籍謄本等取得実費が掛かります。
任意後見人に対する報酬
任意後見契約にて決定します。
任意後見監督人に対する報酬
業務内容と本人の資産の額に応じて、裁判所が決定します。
●受付時間 9:00~18:00
●休業日 土・日・祝祭日(応相談)
無料相談予約受付中

お電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
司法書士:村井 賢介

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。